受注生産と見込み生産の違いとは?効率的な生産方式の選び方と業務改善のポイントを紹介
2025.02.05A0 生産管理
生産現場における受注から生産までのプロセスには、「受注生産」と「見込み生産」の2つがあります。受注生産のことを「Make to Order」、見込み生産のことを「Make to Stock」と英語では言いますが、英語のほうが直接的な表現であるため直感的に意味を理解しやすいでしょう。
製品を作るタイミングが受注より前か、それとも後かで名前が違うだけでなく、それぞれにメリットやデメリットが存在し、生産計画も異なります。生産計画に携わる方は、両者の違いをしっかりと把握しておきましょう。
今回は、受注生産と見込み生産について、基礎知識や両者の違い、メリット、デメリットそれぞれの生産計画の立て方をまとめました。2つの生産形態への理解を深めて、ぜひ生産計画の立案や業務改善にお役立てください。
【目次】
■受注生産と見込み生産の違い
・ 受注生産とは?
・ 見込み生産とは?
・ 見込み生産と受注生産の両方を活用する
■見込み生産が適している製品
・ 需要が安定している製品
・ 大量生産が可能で需要が大きい製品
・ 価格が比較的安価で在庫リスクが低い製品
・ 賞味期限が長く、品質が安定している製品
・ 製品が安定していて、変動が少ない製品
■受注生産が適している製品
・ カスタマイズが必要な製品
・ 高単価で在庫を持ちにくい製品
・ 需要が予測しにくい製品
・ 生産量が少なく、個別設計が必要な製品
・ リードタイムが許容される製品
■生産計画の立て方
・ 生産計画の立て方:受注生産
・ 生産計画の立て方:見込み生産
■生産計画を最適化する方法
■業務効率化のポイント
・ 1. 需要予測の精度向上
・ 2. 在庫管理システムの導入
・ 3. 柔軟な生産対応
■生産スケジューラの特徴
・ 生産スケジューラ「Asprova APS」
■おわりに
受注生産と見込み生産の違い
生産方式には、顧客のニーズに応じて「受注生産」と「見込み生産」という2つの方法があります。それぞれに特徴があり、適した製品や業務内容が異なります。
受注生産とは?
受注生産は、顧客からの注文を受けてから製造を始める生産方式です。顧客ごとに異なるニーズや仕様に合わせて生産するため、特注品や少量多品種生産に適しています。この方式のメリットは、無駄な在庫を抱えないことですが、製造を開始するまでに部品の用意などが必要なため、納期が長くなる傾向があります。
受注生産は、高額な商品や一品ものを作る場面で活用されます。たとえば、特注の家具や船舶、産業用機械など、顧客の要望に応じた製品が該当します。これらはすべて少量生産であり、製造にかかるコストが高いため、受注が確定してから生産することが適しています。受注生産では、製品が過剰に製造されることがなく、在庫の管理コストを削減できますが、その分、リードタイムが長くなりやすいため効率的なスケジューリングが求められます。
見込み生産とは?

見込み生産は、将来の需要を予測して製品をあらかじめ生産し、在庫として保管する生産方式です。特に、日用品や食品、加工品など、日常的に需要があり、販売予測が立てやすい製品に向いています。製品が在庫として保管されているため、注文が入ればすぐに出荷できるのが大きなメリットです。特に、大量生産が可能な製品に適しています。たとえば、洗剤やトイレットペーパー、ペットボトル飲料といった消耗品、あるいは家電の基本モデルなどがこれに該当します。この生産方式では、大量に製品を生産することで、1つあたりの製造コストを抑えることができます。しかし、需要予測が外れた場合には、過剰在庫を抱え、保管コストや廃棄のリスクが生じることもあります。そのため、正確に需要予測する技術や経験が重要です。
見込み生産と受注生産の両方を活用する
多くの企業では、見込み生産と受注生産の組み合わせを活用して、生産効率と顧客対応のバランスを取っています。この組み合わせを「ハイブリッド戦略」と言います。このハイブリッド戦略では、標準的な製品を見込み生産で大量に製造し、在庫として保持しておく一方で、顧客の要望に応じた特注部分やカスタマイズ部分を受注生産で対応します。
たとえば、自動車業界では、基本モデルを見込み生産であらかじめ製造し、一般的なニーズにはすぐに供給できる体制を整えています。そして、特別なオプションやカスタマイズが必要な車種については、顧客から注文を受けてから生産する受注生産を採用しています。このように、生産効率を高めながらも、顧客の多様なニーズに柔軟に対応できるのがハイブリッド戦略の特徴です。
見込み生産が適している製品
見込み生産は、製品の需要を予測してあらかじめ生産し、在庫として保管する方式です。需要が安定している製品や、大量生産が可能でコスト削減が見込める製品に適しています。事前に在庫を確保することで、迅速な納品が可能となりますが、正確な需要予測がカギとなります。ここでは、見込み生産に適した製品の特徴を詳しく解説します。
需要が安定している製品
日用品や食品など、日常的に使用される製品は見込み生産に適しています。これらの製品は、消費されるペースが一定で、季節や市場の変動によって大きく左右されることが少ないため、安定した需要が見込めます。たとえば、洗剤やトイレットペーパー、ペットボトル飲料、保存食などがその代表例です。こういった製品は、日々消費されるため、予測がしやすく、見込み生産によって効率的に供給することが可能です。
大量生産が可能で需要が大きい製品
家電製品のように、大量生産が可能で需要が広範囲にわたる製品も見込み生産に適しています。冷蔵庫や洗濯機などの標準モデル、自動車の基本モデルなどがその一例です。これらの製品は、多くの消費者に広く必要とされ、一定の需要があるため、生産計画を立てやすいです。また、大量生産することで1つあたりの製造コストを抑えられ、効率的な販売が可能です。
価格が比較的安価で在庫リスクが低い製品
文房具や靴下、使い捨ての消耗品など、低価格で比較的在庫リスクが少ない製品も見込み生産に向いています。これらの製品は、多少の在庫が残ったとしても、値引きセールなどで容易に処分でき、在庫を持つことで発生するリスクを抑えられます。また、単価が低いと保管や管理コストが全体の利益に与える影響も少なく済みます。
賞味期限が長く、品質が安定している製品
賞味期限が長い製品や、長期間保管しても品質が劣化しにくい製品も見込み生産の対象となります。たとえば、缶詰や加工食品、長く使用される消費財などが該当します。これらの製品は、在庫として一定期間保管していても品質が維持されやすく、廃棄のリスクが低いため、見込み生産が可能です。また、安定した品質が求められるため、供給に関するトラブルが少なく、見込み生産のメリットを活かしやすいです。
製品が安定しており、変動が少ない製品
標準化された工業製品も、見込み生産に適しています。たとえば、標準部品や建築資材、基礎化学品などが該当します。これらの製品は、仕様の変更が少なく、一定の需要があるため、見込み生産によって効率的に供給することが可能です。また、工業製品の場合、大量に必要とされるため、生産計画を立てやすく、コスト管理がしやすいです。
受注生産が適している製品
受注生産は、顧客からの注文を受けた後に生産を開始する方式です。この方式は、製品にカスタマイズが必要な場合や、高価格で大量の在庫を持つことが難しい製品に適しています。事前に製品を作らず、注文後に生産を始めるため、無駄な在庫を持たずに効率的に生産できますが、納品までの時間(リードタイム)が長くなりがちです。ここでは、受注生産に適した製品の特徴について詳しく解説します。
カスタマイズが必要な製品
オーダーメイドや特注品のように、顧客の要望に合わせたカスタマイズが必要な製品には受注生産を行います。たとえば、注文住宅やオーダーメイドの家具、オーダースーツなどがこの例です。これらの製品は、顧客ごとに異なる仕様やデザインが必要になるため、事前に生産することが難しく、注文が確定してから設計と製造を進めるのが一般的です。
また、工場で使われる製造機械や医療機器、工場の生産ライン用設備なども受注生産に適しています。こういった設備は、各顧客の業務内容や設置場所に合わせたカスタマイズが必要となるため、受注後に設計を開始し、それに基づいて製造を行います。
高単価で在庫を持ちにくい製品
高額な製品で、少量生産される製品は、在庫を持つリスクが大きいため、受注生産が向いています。たとえば、船舶や航空機、大型の工業機械などは、製造コストが非常に高く、事前に在庫を持つことは非効率です。これらの製品は、少量の受注であっても十分な利益が見込めるため、在庫を抱える必要がなく、コストの管理がしやすいのが特徴です。
また、医療機器や精密機器の中で、顧客ごとのニーズに合わせた特注品は、受注生産が適しています。たとえば、カスタマイズされた医療検査装置などは、使用する環境や条件に応じて仕様を変更する必要があるため、受注生産されます。
需要が予測しにくい製品
受注生産は、需要が安定していない製品にも向いています。たとえば、特殊な工具や金型、試作品のように限定的な需要を持つ製品は、事前に生産しても売れ残る可能性が高いため、注文を受けてから生産すると無駄が少なくなります。研究開発用の製品も同様で、プロトタイプや実験機器、試作部品など、変動しやすい需要に対応する製品は、少量生産が多く、事前に作り置きすることが難しいため、受注生産が適しています。
生産量が少なく、個別設計が必要な製品
多品種少量生産が求められる製品にも、受注生産が適しています。たとえば、産業機械の中には、カスタマイズが多く、個別に設計される工作機械などがあります。こうした製品は、標準品として大量に作るのではなく、顧客のニーズに合わせて一つひとつ設計して生産する必要があるため、受注生産が効率的です。
また、アート作品や特注の装飾品、ジュエリーなども受注生産に向いています。これらの製品は、個別のデザインや特注仕様が多く、受注が確定してから製造を始める方が無駄なく生産できます。
リードタイムが許容される製品
受注生産は、納品までの時間を許容できる製品にも適しています。たとえば、特注の家具やオーダーメイドの住宅などは、顧客が納品までのリードタイムを受け入れやすいため、事前に在庫を持たず、注文後に生産を開始する方が効率的です。このような製品では、顧客が高い品質を求めており、多少の納期がかかっても満足度が維持されることが多いです。
生産計画の立て方

受注生産と見込み生産、どちらの生産形態においてもデメリットがありますし、企業や現場それぞれに課題が存在します。考えられるリスクや危険性を事前に把握し、なるべく回避するためにも、過去の実績やデータを参考にしながら生産計画を最適化していくことが大切です。また、計画に変更やトラブルが生じた際、柔軟に対応する環境を用意できているかがスムーズな改善のポイントとなります。 ここからは、それぞれの生産計画の立て方について解説します。
生産計画の立て方:受注生産
受注生産の生産計画では、まず受注予測を行います。受注予測は過去の実績や販売データを参考にして行います。製品を製造するための原材料や部材の中には、手配や調達に時間がかかるものもあります。生産計画は、それらの調達期間も考慮したうえで立案していきましょう。
材料に「製造品」が含まれる製品では、特に調達のリードタイムに注意が必要です。リードタイムの予測を誤ってしまうと納期遅れのリスクが生じるだけでなく、生産計画全体がずれてしまいかねません。予測するリードタイムにある程度の余裕(バッファ)を持たせる、仕入先のリードタイムをこまめに確認する、場合によっては改善を求めるなど、計画を見直しながら進めていくことが大切です。
生産計画の立て方:見込み生産
見込み生産の生産計画では、精度の高い販売予測ができるかがポイントです。販売予測の精度が高ければ過剰在庫を減らせますし、在庫が足りないという状況も防ぐことができます。
販売予測の精度を高めるには、市場の動向や顧客ニーズの把握が重要です。市場調査やヒアリング、リサーチなどは入念に行いましょう。販売予測を月別の販売計画に反映させて生産計画を立てていきます。ただし、見込み生産はあくまでも予測や見込みであり、想定どおりに受注できるとは限りません。 受注を逃さないためにも、仕様変更や納期の変更依頼、飛び込み依頼など、顧客からの要望に柔軟に対応できる姿勢を示せるかが重要です。さまざまな依頼に迅速に対応できると、顧客満足度が向上し、市場での競争優位性の獲得につながります。
生産計画を最適化する方法
進捗管理や部材の調達状況、在庫把握、人材管理など、生産計画をスムーズに進めるためには多くの業務や工程における情報管理がポイントとなります。このような情報を一元的に管理し、効率化できるのが生産管理システムです。
生産管理システムを導入しているのに「あまり収益が高まらない」、「これ以上業務効率が改善しない」といった場合は、生産計画に把握できていない問題点があることが考えられます。
使用しているツールを見直す、「4M:Man(人)・Machine(機械)・Material(材料)・Method(方法)」の管理で部分的な見直しを実行するなど、計画をこまめに修正し最適化していくことが大切です。
生産管理システムには業種や生産形態によって相性があり、必要な機能も異なります。システムを導入しているのに上手な生産計画が立案できないという場合は、今使っているツールが本当に自社に適しているかを、改めて見直す必要があります。
業務効率化のポイント
見込み生産を効率化するには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。これらを実施することで、無駄な在庫や生産コストを抑えながら、顧客の要望に素早く応じる体制を整えることができます。以下のポイントを踏まえ、業務の効率化を目指しましょう。
1. 需要予測の精度向上
見込み生産を行うには、需要予測の精度が非常に重要です。AIやデータ分析を活用して、過去の販売データや市場の動向を分析し、より正確な予測を行うことで、無駄な生産や過剰在庫を避けることができます。
たとえば、季節ごとの販売傾向や過去に需要が高まった時期を分析し、それを次の生産計画に反映させることができます。長期的なデータをしっかりと分析することで、より精度の高い予測が可能になります。
また、AIや自動化されたデータ分析ツールを活用することで、人手では処理しきれない複雑なデータも短時間で分析でき、販売パターンを見つけ出し、需要予測の精度を向上させることができます。こうした自動化は、効率的な生産計画を実現するための重要な要素です。
2. 在庫管理システムの導入
在庫を効率的に管理するためには、在庫管理システムの導入が有効です。このシステムを導入することで、リアルタイムで在庫状況を把握でき、過剰在庫や欠品を防ぐことが可能です。
リアルタイムでの在庫管理が可能なシステムを使えば、常に最新の在庫状況を確認しながら、必要に応じて生産量を調整できます。過剰在庫や欠品を自動的に検知する機能があるため、発注や補充のタイミングを逃さず、効率的に管理できます。
また、在庫データを自動で更新・管理することで、手動で発生しがちなミスやデータ入力の遅れを防止できます。各倉庫間での在庫間移動や補充も自動化できるため、無駄な在庫を減らし、効率的な運用が可能です。
さらに、需要に応じた最適な在庫量を設定することで、在庫切れを防ぎつつ、過剰な在庫を持たないように管理できます。過去のデータを基に在庫量を設定することで、需要が変動しても柔軟に対応でき、倉庫スペースを有効に活用しながら、在庫管理にかかるコストも削減を目指せます。
3. 柔軟な生産対応
市場の変化や顧客の要望に対し、迅速かつ柔軟に対応するためには、生産体制の見直しが必要です。製品によって見込み生産と受注生産を使い分けることで、効率的な生産体制を維持しながら、顧客のニーズにも対応できる体制を整えることができます。
市場や顧客ニーズの変化に即応するために、生産量やスケジュールを柔軟に変更できる体制を構築することが求められます。需要が急激に増減する場合でも、すぐに対応できるような生産計画を整備し、タイミングや数量を適宜調整できる仕組みが重要です。
また、見込み生産と受注生産を適切に使い分けることで、効率をさらに高めることができます。たとえば、需要が安定している製品には見込み生産を採用し、少量生産やカスタマイズが必要な製品には受注生産で対応することが有効です。これにより、無駄な在庫を抱えることなく、効率的な生産を実現しながら顧客のニーズに合った製品を提供できます。
生産スケジューラの特徴
スムーズでスピーディーに生産計画を立案したいなら、専門ソフトの導入が効果的です。
Excelなどの表計算ソフトでスケジューリングするのも可能ではありますが、変更が生じた際に柔軟に対応しにくい、リアルタイムでの把握に難点がある、属人化リスクがついてまわるなど、これまでの課題をぬぐえません。
生産計画立案ソフト(生産スケジューラ)なら変更にもすぐに対応できるうえ、現場のリアルタイムな状況の正確な把握が可能です。ただし、生産スケジューリングができるソフトの中には、受注形態に合わせたソフトもあれば業種ごとに特化したソフト、自社業務に合うようにカスタマイズをしてもらえるソフトなど、さまざまなものが販売されています。 自社の生産計画に求められる機能が搭載された、最適なソフトを選びましょう。現場管理を円滑化したい、生産計画を最適化したい、生産スケジューラについてさらに詳しく知りたいという方は以下のページをご覧ください。
生産スケジューラ「Asprova APS」
アスプローバ株式会社が提供する生産スケジューラ「Asprova APS」は、生産計画の自動立案はもちろん、固定リードタイムでのスケジューリングや設備の生産能力を加味したスケジューリングなど、多面的な計画立案ができるソフトです。材料や製品の在庫を適切に保ちつつ、需要の変化にも迅速に対応できるように設計されています。
多品種・多工程に対応可能で、調達から生産、配送まですべての現場に求められる機能を網羅。業種ごとの最適な使い方や導入ノウハウなど、わからないことがあればいつでも聞けるサポート体制も整えています。
おわりに
受注生産と見込み生産は、それぞれ異なる製品や業務に適しています。受注生産は顧客のニーズに合わせたカスタマイズが必要な製品や高価な製品に向いており、見込み生産は需要が安定している製品や大量生産に適しています。これらの生産方式をうまく使い分けることで、効率的な生産体制を整え、無駄な在庫やコストを削減することが可能です。
業務効率化のためにAIや在庫管理システムを導入する際は、過去の実績や予測データを活用した計画立案が重要です。そのためには、生産スケジューラの導入が効果的でしょう。生産スケジューラは、業種や生産形態、管理方法によって適したシステムが異なります。システムの導入を検討する際には、課題を解決できるかはもちろん、現場環境に合わせた機能が搭載されているかを含めて選ぶようにしましょう。
コラム編集部
最新記事 by コラム編集部 (全て見る)
- S&OP(Sales and Operations Planning)~生産スケジューラ連携 - 2025年4月9日
- 在庫管理:ムダを削減し、欠品を防ぐ最新手法 - 2025年4月9日
- MESシステム~生産スケジューラ連携でPDCAサイクルを最適化 - 2025年4月9日

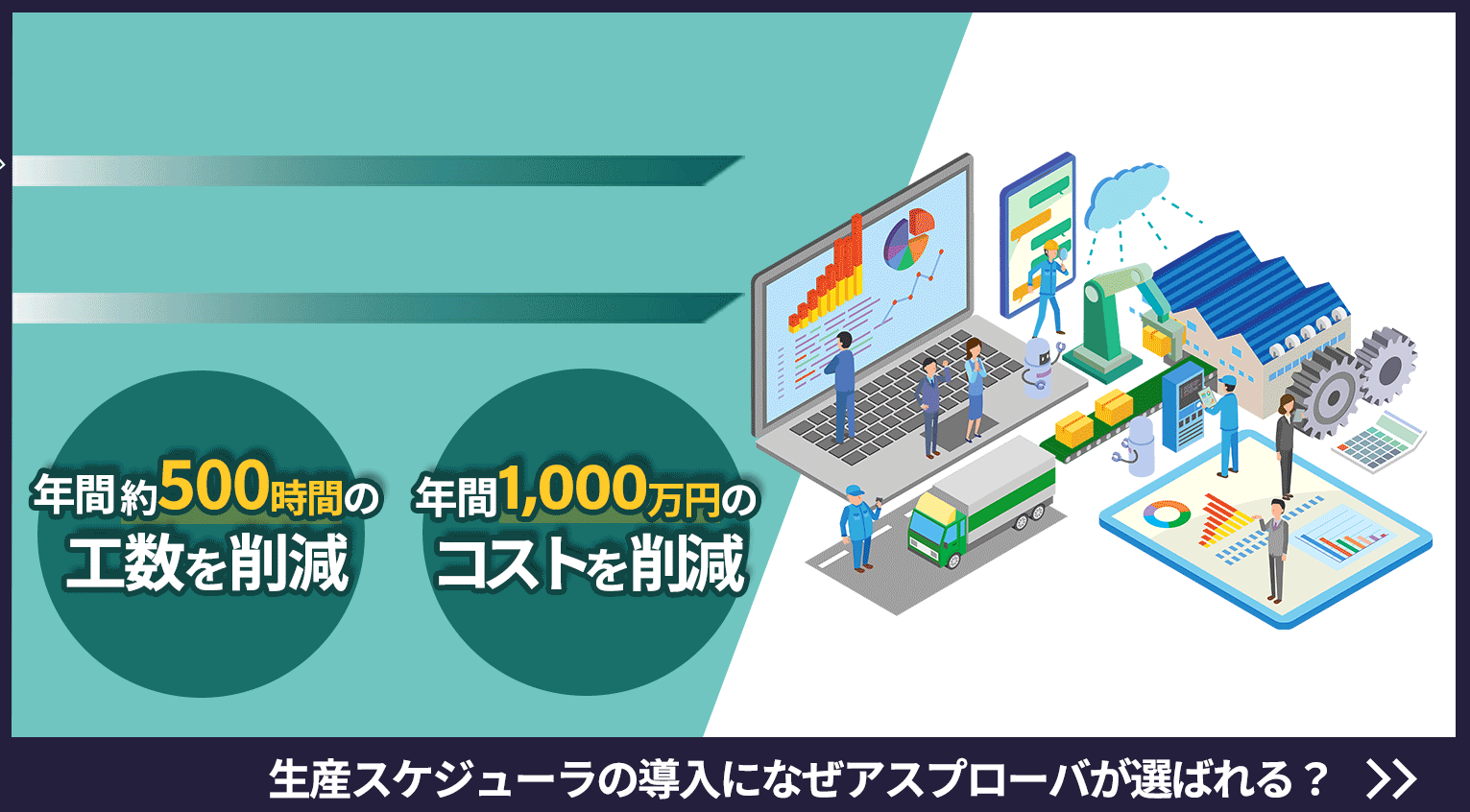
 なぜDXを進めることで生産性が向上するのか?メリットやデメリット・方法を徹底解説
なぜDXを進めることで生産性が向上するのか?メリットやデメリット・方法を徹底解説 QCDとは?生産管理において重要な理由や改善方法・踏むべきステップを解説
QCDとは?生産管理において重要な理由や改善方法・踏むべきステップを解説 MRPとは?メリットやMRP2やAPSとの違いをわかりやすく解説
MRPとは?メリットやMRP2やAPSとの違いをわかりやすく解説 期間別生産計画(大日程・中日程・小日程)はどうやって立てる?
期間別生産計画(大日程・中日程・小日程)はどうやって立てる? Excelで工程管理表を作成する方法
Excelで工程管理表を作成する方法 期間別生産計画(大日程・中日程・小日程)はどうやって立てる?
期間別生産計画(大日程・中日程・小日程)はどうやって立てる?