期間別生産計画(大日程・中日程・小日程)はどうやって立てる?
2025.02.06A0 生産管理
生産計画は製造に欠かせない工程です。計画は、「大日程計画」「中日程計画」「小日程計画」の3つの期間に分けて行うのが一般的です。本記事では、それぞれの計画の特徴や具体的な立て方について解説します。
【目次】
■「期間別生産計画」とは?分け方をご紹介
・大日程計画とは
・中日程計画とは
・小日程計画とは
■計画作成を自動化!「Asprova」のススメ
■大日程計画の立て方
・生産量の予測と需要を分析
・設備投資
・人員計画
■中日程計画の立て方
・受注に基づいた生産量の調整
・資材調達の計画
■小日程計画の立て方
・現場での作業スケジュール調整
・ボトルネックの改善
■期間別生産計画で得られる効果
・納期の遵守
・在庫削減
・生産効率の向上
■生産計画は「安定した製造」を実現する重要なポイント
「期間別生産計画」とは?分け方をご紹介
期間別生産計画とは、生産活動を長期、中期、短期の3つの期間に分けて計画する方法です。これにより、企業は生産活動を効率的に行い、需要の変化に柔軟に対応することが可能となります。それぞれの計画「大日程計画」「中日程計画」「小日程計画」の特徴や具体的な立て方について詳しく解説します。
大日程計画とは
大日程計画は半年から1年の長期計画で、企業戦略に基づき、生産方針を決めるのが特徴です。新製品導入や設備投資、人員確保を行い、需要予測と市場調査で生産量とリソースを計画します。
大日程計画には、下記のような内容が含まれます。
- 長期的な生産方針や大まかな年間計画
- 過去の販売データや市場動向を基にした需要予測
- 設備の導入や投資計画
- 新製品の導入や改良計画
- 人員の配置や育成計画
中日程計画とは
中日程計画は1~3か月の中期的な生産計画です。受注や在庫に基づき生産量を決定し、生産ラインの稼働率を最適化します。原材料の購買計画も行い、現場の効率を最大化するのが目的です。
中日程計画には、次の項目が含まれます。
- 受注内容や在庫を基にした生産量の決定
- 原材料や部品の発注と購買計画
- 生産設備の稼働状況の確認とシフトの調整
- 1~3か月先の在庫管理と見直し
- 週、月の見直しと市場変動への対応
小日程計画とは
小日程計画は1日から1週間の短期計画です。日々の作業スケジュールやシフト管理、進捗の調整を行います。生産性向上のための詳細な計画です。日々の作業を監視し、遅れが出たら都度調整を行います。
小日程計画には、次の項目が含まれます。- 現場での作業指示や日々の計画の策定
- 作業順序やシフト管理、機械や設備の稼働スケジュールの決定
- 日々の進捗確認と遅れの監視
- 作業員の割り当て調整によるリソースの最適利用
- 予期せぬトラブルや遅延に備えた柔軟なスケジュール管理
計画作成を自動化!「Asprova」のススメ
とはいえ、生産スケジューラの導入を検討する方の中には、「結局どの生産スケジューラを選ぶべき?」という疑問を持つ方も多いでしょう。 期間別生産計画に役立つ生産スケジューラとして、「Asprova」を導入してみませんか。
Asprovaの強みは、資源(設備や人員)のキャパシティを超えないように作業を配置する「有限能力スケジューリング」です。可視化された工程情報や従業員の能力情報などを基に、最適かつ無理のない生産計画を自動で立案します。本記事で紹介している大日程計画、中日程計画、小日程計画も立てられるほか、中・短期計画を連動させ、計画の変更も容易です。
特に、小日程のスケジューリング精度や立案サイクルを上げたい企業は、Asprovaがおすすめです。以下の専用ページでは、Asprovaの機能や導入方法・成功事例を紹介しています。ご興味のある方は、まずはこちらをご覧ください。
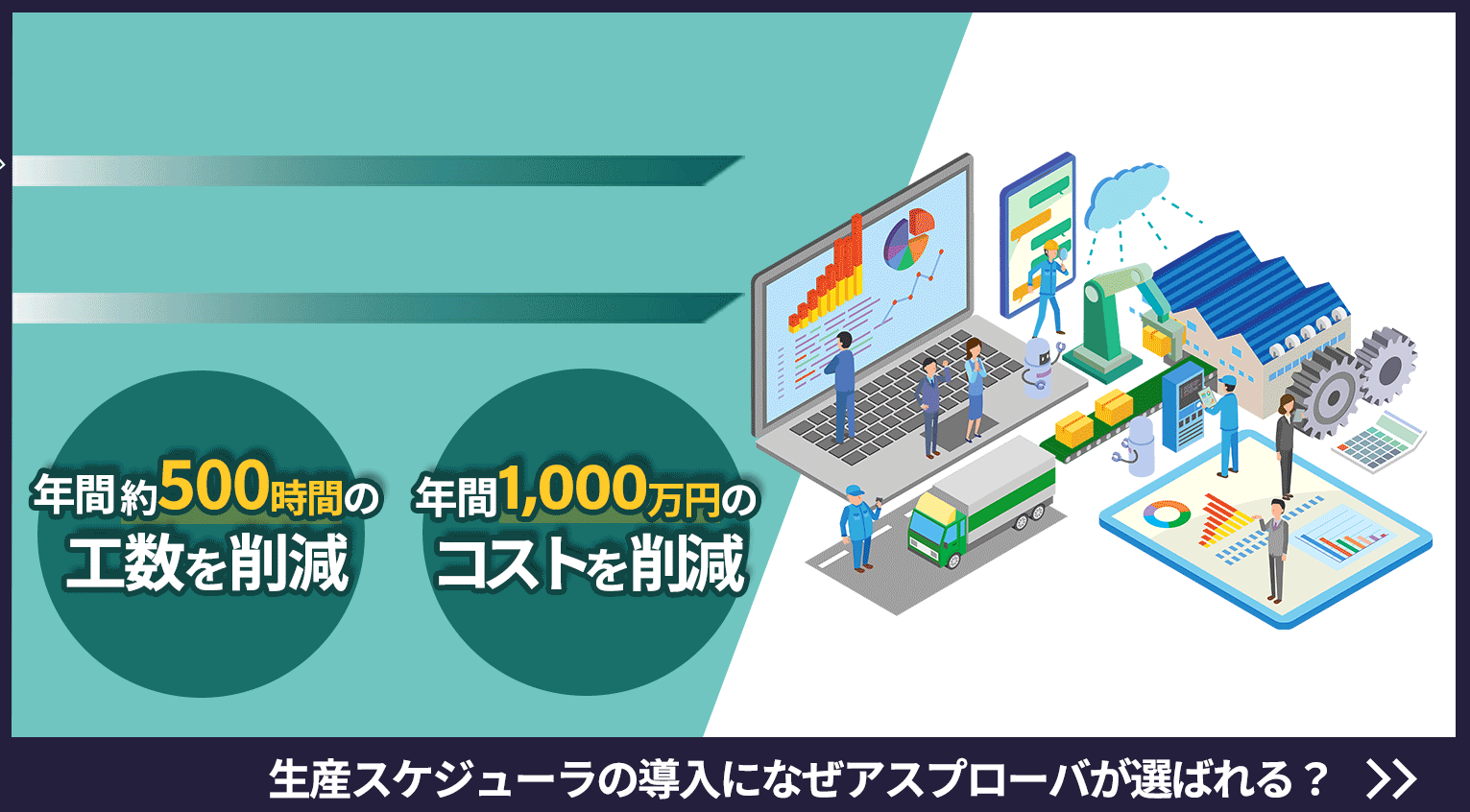
大日程計画の立て方
大日程計画は、半年から1年、あるいは数年にわたる生産活動の方針を決定します。ここでは、大日程計画の立て方を解説します。
生産量の予測と需要を分析
需要予測には、過去の「販売実績データ」や「在庫数」、「販売チャネル別の傾向」などの社内データが不可欠です。これには月ごとの売上や四半期ごとの販売実績、在庫の変動、顧客の年齢や購買頻度といった情報が含まれ、将来の需要を予測する基盤として活用します。たとえば、地域や季節ごとの需要の違いを把握することで、過剰在庫や欠品リスクを減らすための在庫調整に役立ちます。
さらに、天候や経済状況、為替レートといった「外部要因データ」も需要予測において重要です。季節により需要が変動する商品では、気温や経済トレンドを踏まえた予測が効果的です。たとえば、夏季に冷たい飲み物やアイスクリームの需要が増えるケースでは、前もって準備することで販売機会を逃さずに対応できます。これらのデータの活用によって、生産計画の精度が高まるでしょう。
設備投資
予測された生産量に基づき、設備投資の必要性を判断します。まず、現行の設備が生産目標を達成するための能力を持っているかを評価。設備が老朽化している場合、更新や改修を検討して生産性を維持することが重要です。
たとえば、最新技術や機械の導入が求められる場合もあるでしょう。その際、生産ラインの自動化が、需要増に対応するためによく行われる投資です。ロボットの導入や機械の自動制御装置により、作業の省力化や品質の安定化が可能となり、結果的に生産効率が高まります。組立工程では、作業の柔軟性を持たせるためにロボットの先端部分を切り替えることで、異なる工程に対応できるシステムを導入するケースがあります。
また、検査工程では画像処理システムを導入することで異物や製品の欠けなどを自動検査し、人的負担を減らしつつ精度を向上させることが可能です。さらに、品質管理における設備投資としては、製造プロセス中の温度や湿度、圧力といった品質に影響を与える要素を常時モニタリングするセンサーの導入が考えられるでしょう。
これらの設備投資は、コスト面でも大きな影響を与えるため、十分なシミュレーションとコスト回収の見込みを立て、慎重な判断が求められます。
人員計画
設備の確認と並行して、必要な人員を確保します。専門的な技術や知識を持つ作業員が不足している場合は、早急に人材採用計画も併せて立てましょう。
また、生産性の向上や品質の安定が必要であれば、既存の従業員へのトレーニングも行いましょう。トレーニングによって一人ひとりの生産性が高まれば、需要の増加にも対応が可能です。
中日程計画の立て方
中日程計画は1~3か月の中期生産計画で、受注状況や在庫に基づき生産量や資材の調達を具体的に決定します。ここでは、受注に基づいた生産量の調整と資材調達の計画について解説します。受注に基づいた生産量の調整
中日程計画ではまず、顧客からの受注に基づいて生産量を決定します。注文のタイミングや納期を考慮し、生産ラインの稼働を準備。受注が多い時期には、設備や人員の調整を行い、生産ラインの稼働率を高めます。また、繁忙期に備えて設備のメンテナンスや人員の配置を事前に調整し、計画に基づいた生産ができるようにしましょう。受注内容の変更があった場合は、計画の見直しも必要です。準備とあわせて、変更に対応できる柔軟さも残しておくことが大切です。資材調達の計画
中日程計画では、生産量に基づき必要な材料や部品の調達計画を策定します。調達にかかるリードタイムを考慮し、欠品や過剰在庫を防ぐために適切なタイミングで発注しなくてはいけません。たとえば、納入までに数週間かかる材料は早めに発注し、生産スケジュールに支障をきたさないようにしましょう。
調達数量は慎重に管理し、適正な量を発注して無駄な在庫を避けます。材料不足を防ぐためにサプライヤーと密に連携し、安定した供給体制を維持しなくてはならないでしょう。また、定期的に在庫を確認し、季節変動や需要の変化に応じて発注量を調整。こうして、安定した材料供給を維持し、生産ラインの効率を高めることが、顧客からの要望に対応するためにも重要です。
小日程計画の立て方
小日程計画は、1日から1週間単位で立てられる短期的な生産計画で、現場での実際の作業を具体的に指示します。ここでは、現場での作業スケジュール調整とボトルネックの改善について解説します。
現場での作業スケジュール調整
小日程計画では、作業スケジュールを適切に調整することが重要です。各作業に必要な人員や機械を割り当て、開始日と完了予定日を設定。作業の優先順位を明確にし、重要な工程から進めます。これにより、進捗を把握しやすくなり、納期を守ることが可能です。
もし、進捗に遅れが出た場合は、追加リソースを投入し、作業時間を調整。また、作業量に応じて道具や機械の配置を最適化し、生産効率を高めるといった方法もあるでしょう。毎日の進捗を確認して必要に応じてシフトや作業内容を調整し、遅延を防ぐことが大切です。
ボトルネックの改善
生産工程でボトルネックが発生すると、全体の生産速度に影響を与えます。
小日程計画では、ボトルネックとなる工程を早急に特定し、改善することが重要です。まず、時間がかかりすぎる工程や遅延が頻発する箇所を分析します。次に、ボトルネックを解消するための対策を検討。たとえば、機械の稼働率を改善するために定期的なメンテナンスを行い、人員不足の場合はシフトを見直し、作業員の配置を調整します。このように、作業負荷を分散させ、特定の作業の遅延を防ぎましょう。
期間別生産計画で得られる効果
適切に立てられた期間別生産計画は、企業の生産性向上につながります。ここでは、具体的な効果について紹介します。
納期の遵守
期間別の生産計画を立てることで、各工程の進捗が詳細に管理でき、納期の遵守がしやすくなります。たとえば、月単位や週単位のスケジュールを設定し、製造過程の状況を定期的に見直すことで、予定通りに納品できる体制を整えられるでしょう。事前に計画を整えることで、予期せぬトラブルにも柔軟に対応でき、納期遅れのリスクを抑えられます。
また、期間別の計画は、製造と出荷をスムーズに進めるためにも欠かせないものです。工程ごとに適切な管理が行えるようになれば、部門間の調整もスムーズになり、全体としても納期を守りやすくなるでしょう。
在庫削減
期間別の生産計画は、在庫量の適正化にも役立ちます。特に、月次や週次の販売予測に基づき、過剰な在庫を持たないよう管理を徹底することで、保管コストを抑えた運営が可能です。また、無駄なスペースを削減することは、資金の流れを改善するうえでも効果的です。
さらに、期間別計画によって、季節変動や需要の変化による在庫の調整もしやすくなります。必要な時期に必要な在庫が確保でき、滞ることなく生産できます。販売予測にも基づいているため、需要と供給のバランスが取りやすくなり、在庫不足による生産遅延も防げるでしょう。
生産効率の向上
期間別生産計画によって生産性が向上します。
まず、リソースを最適に活用し、在庫管理を適正化し、納期を遵守しやすくなる点にあります。期間ごとの計画を用いることで、必要な人員や設備を効果的に配置し、無駄を減らして稼働率を高めることが可能なためです。また、需要予測に基づき在庫を適切に調整することで、過剰在庫や欠品のリスクを軽減し、保管コストの抑制と安定供給が行えます。さらに、中・小日程計画を通じて各工程の進捗を確認し、計画通りの進行を図ることで、納期を守りやすくなり、遅延による生産性の低下を防げます。
生産計画は「安定した製造」を実現する重要なポイント
期間別生産計画の「大日程計画」「中日程計画」「小日程計画」は、安定した製造を保つために大切です。これらの計画が明確に立てられていると、生産活動が滞りなく進み、安定した供給を維持できます。
一方で、生産計画が不明確な場合、納期の遅れや在庫の過剰や不足といった問題が発生しやすくなります。こうしたトラブルは企業の信頼性を損なう原因にもなるため、どの製品を生産する場合でも計画はしっかりと立てなくてはいけません。
ただし、全体の流れを把握し、詳細な計画を立て続けることは容易ではありません。特に、すべての工程とリソースを常に正確に管理するのは難しいため、生産スケジューラを活用してみましょう。
もし具体的なツールを検討中であれば、当コラムで紹介した生産スケジューラ「Asprova」をお試しください。無料体験版もご用意しております。このほか、Asprovaの資料請求なども承っていますので、詳しくは以下のお問い合わせページからお申し込みください。
コラム編集部
最新記事 by コラム編集部 (全て見る)
- 納期管理:生産スケジューラの活用 - 2025年4月14日
- スケジューリング技術の応用による生産性の改善 - 2025年4月14日
- Lean Manufacturing~生産スケジューラの活用で最適な生産を - 2025年4月14日

 なぜDXを進めることで生産性が向上するのか?メリットやデメリット・方法を徹底解説
なぜDXを進めることで生産性が向上するのか?メリットやデメリット・方法を徹底解説 QCDとは?生産管理において重要な理由や改善方法・踏むべきステップを解説
QCDとは?生産管理において重要な理由や改善方法・踏むべきステップを解説 MRPとは?メリットやMRP2やAPSとの違いをわかりやすく解説
MRPとは?メリットやMRP2やAPSとの違いをわかりやすく解説 生産計画に不可欠な主資源・副資源とは?効率的な運用と管理のポイントを解説
生産計画に不可欠な主資源・副資源とは?効率的な運用と管理のポイントを解説 Excelで工程管理表を作成する方法
Excelで工程管理表を作成する方法 期間別生産計画(大日程・中日程・小日程)はどうやって立てる?
期間別生産計画(大日程・中日程・小日程)はどうやって立てる?