生産スケジューラを短い時間で運用開始するポイント
2024.06.24A1:生産計画・スケジューリング生産スケジューラを導入する期間は、対象工程が1つなどの小規模プロジェクトでは数カ月から6カ月程度、複数工程を含む中規模プロジェクトでは6カ月から1年程度、さらに工場全体や調達計画も含む大規模プロジェクトでは1年以上かかる場合もあります。
導入経験者の意見を伺うと、導入期間は規模によって異なるのは当然ですが、目標設定や導入プロセスによっても差が生じるようです。そして、特に変化が激しい現代においては、迅速に生産スケジューラを導入したいと考える企業が増えています。
実際、3カ月程度で運用開始に成功したケースも幾つかかありますので、その取り組み内容をご紹介します。

1.計画担当者を中心に導入を進める
Excelなどのツールから生産スケジューラに移行する際、覚えることが多かったり、操作に慣れなかったり、考え方に違いがあったりなど、計画担当者には大きな負担がかかります。そのため、システムに詳しいシステム部門がしっかり支援することが重要です。
一方、いつまで経っても運用開始できないケースでは、システム部門だけでひたすら検証を続けている事があります。早い段階で計画担当者の意向を汲み入れ、計画担当者を中心にしたプロジェクト進行を行うことで、早く運用開始できるかもしれません。
2.自動化よりも、運用担当者が無理なく運用できることを目指す
計画に絶対的な正解はなく、状況は常に変わります。
システムを開発したり評価する局面では、課題を管理し、消化していく手法が用いられますが、状況が変わるために新たな課題が発生し、なかなか収束しない事があります。特にスケジューリングの自動化を求められているプロジェクトに多いです。
早くに運用開始されたプロジェクトでは、まずは運用担当者が生産スケジューラを使って業務を回せる状態を目指しています。特に自動化は後回しにし、手動調整も含めて運用を開始されています。
在庫削減、リードタイム短縮などの経営にインパクトのある効果も、運用が馴染めば自ずと得られるという考えです。
3.マスタの精緻化にこだわらない
生産スケジューラの運用において悩みの種となるのがマスタです。情報が詳細であれば計画精度は高まるかもしれませんが、維持が困難になる場合も多いです。
早期に運用を開始したプロジェクトでは、迷ったら平均値を用いる方針を取っています。例えば、機械だけなく作業者までも考慮して計画を立てられるのは生産スケジューラの一つの魅力と言えると思いますが、作業者のAさん、Bさんによって作業時間が異なる場合、それぞれをマスタとして登録すると膨大な量となるため、マスタには平均値のみを登録します。
ある程度それまでの業務で行っていた計画の精度を下げてもよい、あるいは見直してでも簡素化を心掛けています。
これらの3つのポイントを抑えることで、スムーズな導入と早くに運用開始することが可能かもしれません。また、プロジェクトが長引く場合の打開策になるかもしれませんので、是非本コラムのことを頭の片隅に置いておいて頂けたらと思います。
(了)
コラム編集部
最新記事 by コラム編集部 (全て見る)
- 納期管理~生産スケジュールの最適化による納期厳守率の向上 - 2025年4月14日
- スケジューリング技術の応用による生産性の改善 - 2025年4月14日
- Lean Manufacturing~生産スケジューラの活用で最適な生産を - 2025年4月14日

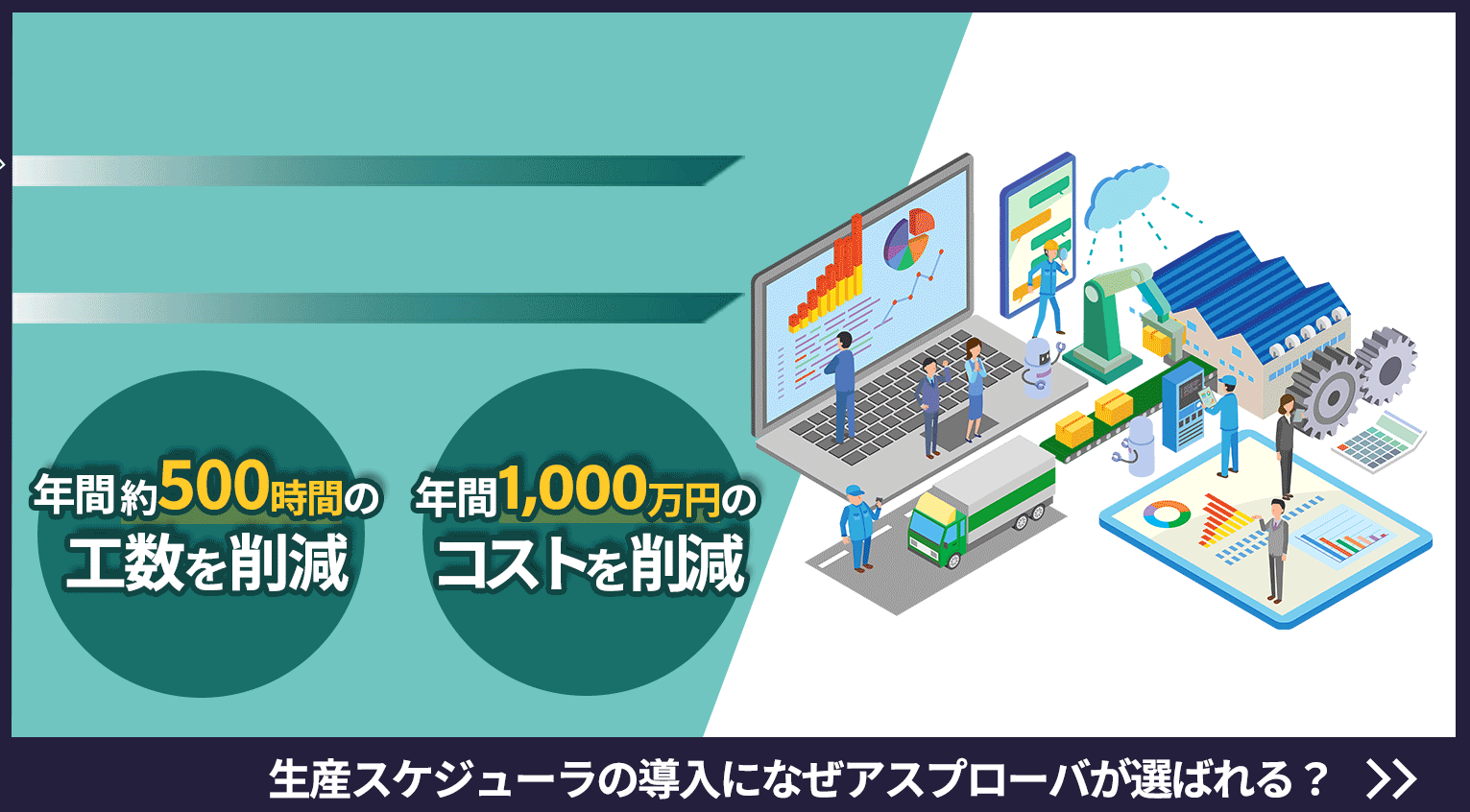
 お客さまの要望から生まれたAsprova新機能 「マーカー」 ガントチャートを見やすく
お客さまの要望から生まれたAsprova新機能 「マーカー」 ガントチャートを見やすく 生産計画とは?Excelで作成するメリット・デメリットや作成方法を解説!
生産計画とは?Excelで作成するメリット・デメリットや作成方法を解説! 生産計画とは?立て方と立案時の注意点
生産計画とは?立て方と立案時の注意点 プロセス製造業の難しい制約を生産スケジューラは考慮できる?〜「資源ロック」とは〜
プロセス製造業の難しい制約を生産スケジューラは考慮できる?〜「資源ロック」とは〜 機械加工工程の生産スケジュール
機械加工工程の生産スケジュール 生産スケジューラを使用した、射出成形のスケジューリングを解説
生産スケジューラを使用した、射出成形のスケジューリングを解説