アスプローバのセミナーで学ぶ:外段取りを考慮した最適な生産スケジューリング
2023.11.08A3:生産スケジューリングの悩み相談製造中に発生する「段取り」は可動率を下げる要因です。以前のコラムでも紹介しましたが可動率(べきどうりつ)とは運転効率を示す指標で、(製造時間÷実操業時間)×100で求められます。
工作機械を使用する場合、金型交換や部品の用意などの段取りはどうしても発生します。そこで多くの製造現場では、機械を停止せずに段取りを行う「外段取り」を行っているかと思います。
しかし、外段取り化を進めたにもかかわらず、実際に設備の可動率を見てみると思ったよりも数字が良くないといったケースはないでしょうか。

アスプローバが開催しているセミナー「効率化生産のための最適スケジューリング~外段取り編~」では、外段取りのスケジューリングの難しさと、その解決方法について紹介しています。
外段取りも考慮したスケジューリングの難しさ
セミナーではまず、外段取りを考慮したスケジューリングの難しさについて紐解いていきます。
スケジューリングを考える際、「外段取り中に品目替えが発生すると、待ち時間が発生する」ことを考慮する必要があります。しかし、外段取りを行っている時間帯に品目替えが発生しないようにある程度まとめ生産をして、なおかつ納期遅れを起こさないようにするのは難度の高い計画です。
さらに金型のメンテナンスも考慮しなければなりません。たとえば一定の使用回数に達したら金型のメンテナンスを行う場合、使用状況も考慮しながらスケジューリングしなければならないのです。
以上のように、外段取りを進めて効率化を図る場合には納期だけでなく、外段取り中に製造できる品目、金型の使用状況も考慮しなければならず、計画業務はとたんに難度が高くなります。
Solverを使った最適化
その解決方法として提示されるのがSolverオプションです。Solverは高難度のスケジューリングに対応するAsprovaの新しいオプションで、人が数時間かけていた計画と同等以上のものを数十秒で導き出します。
セミナーの中盤、Solverを使用したスケジューリングのデモンストレーションが見られます。
これまでの生産スケジューラのロジックで計画すると、可動率は約77%で納期遅れ件数は37件でした。そのため、従来では手修正で納期遅れを無くすように可動率を上げる計画を立てなけばなりません。
それをSolverであればものの数秒で納期遅れ件数0件、可動率100%の計画を導き出してしまいました。なぜか。
それは、Solverが反復改善をするからです。反復改善とは数万通り、数十万通りの計画を試して、その中で最も良い計画を採用する方法です。
外段取りを考慮しながら、なるべくロスの少ない計画を立案したい方は、一度セミナーに参加してはいかがでしょうか。
(了)
コラム編集部
最新記事 by コラム編集部 (全て見る)
- 作業を押し込んで割り付ける~裁量の利くプログラムを開発 - 2025年12月10日
- ユーザーが語る新たなAsprova~ユーザー会2025~ - 2025年12月3日
- 機能の提供からソリューションへ~ユーザー会 2025~ - 2025年12月3日

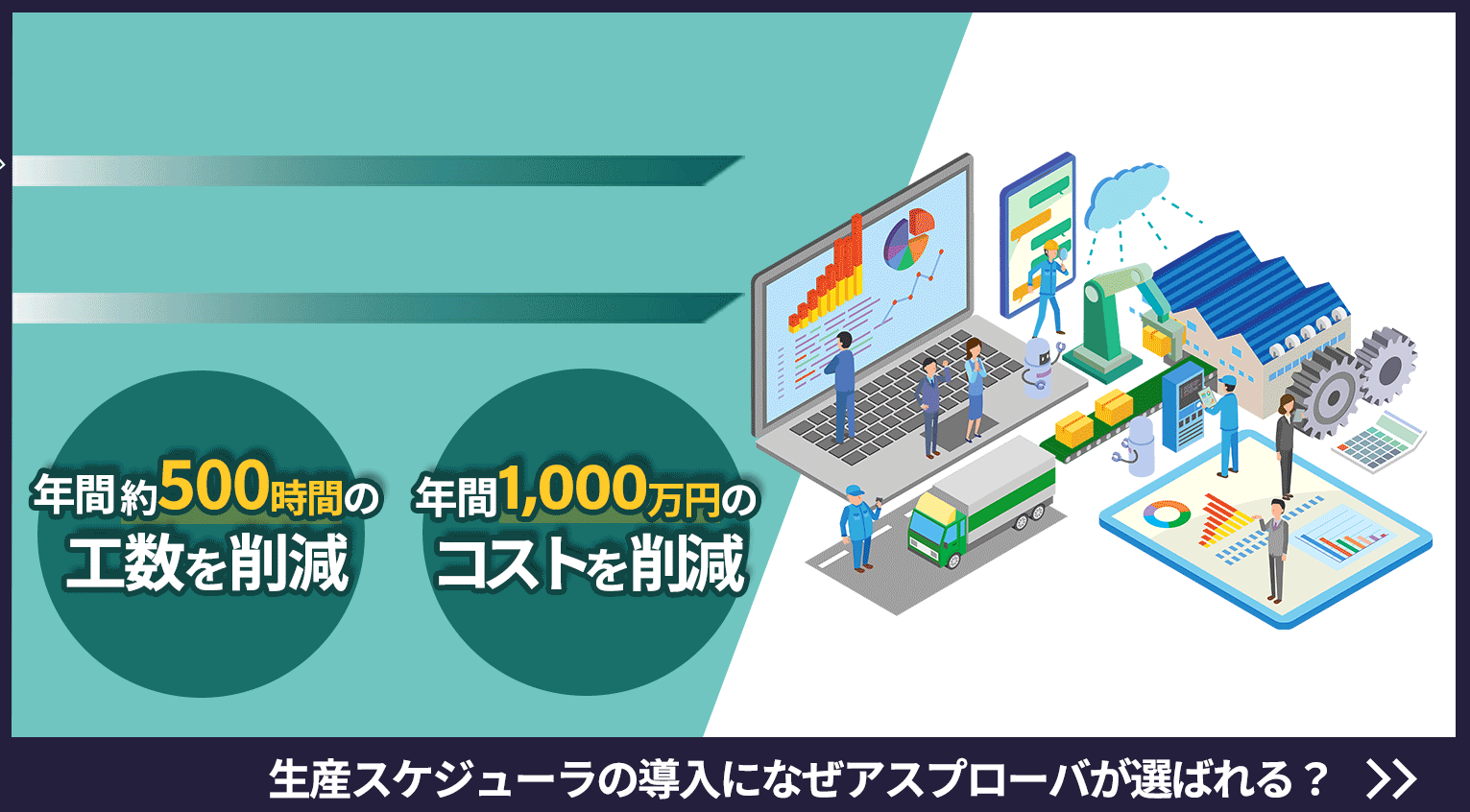
 困ったこと35~システムテストは、どこでテストの完了かわからなかった
困ったこと35~システムテストは、どこでテストの完了かわからなかった 困ったこと35~計画作成方法(コマンド、計画パラメタ)がわからなかった
困ったこと35~計画作成方法(コマンド、計画パラメタ)がわからなかった 困ったこと35~現状業務をどこまで変えたらよいかで迷った
困ったこと35~現状業務をどこまで変えたらよいかで迷った 生産スケジューラを導入すると、どんな効果が期待できますか?
生産スケジューラを導入すると、どんな効果が期待できますか? 生産スケジューラの導入を検討するには?
生産スケジューラの導入を検討するには? システム連携でお困りの方に、基幹業務システムとAsprovaの連携パターンを紹介
システム連携でお困りの方に、基幹業務システムとAsprovaの連携パターンを紹介