困ったこと35~何ができて、何ができないのかわかりにくかった
2024.03.01A3:生産スケジューリングの悩み相談生産性向上をめざして新しいツールを入れてみよう-。そんな企業が増えています。生産スケジューラに限らず、新しいツールを採用しようとするときには「何ができて、何ができないのか」という疑問が生じます。これをどう解決していけばいいのか、生産スケジューラAsprovaを念頭に、策を示してみます。
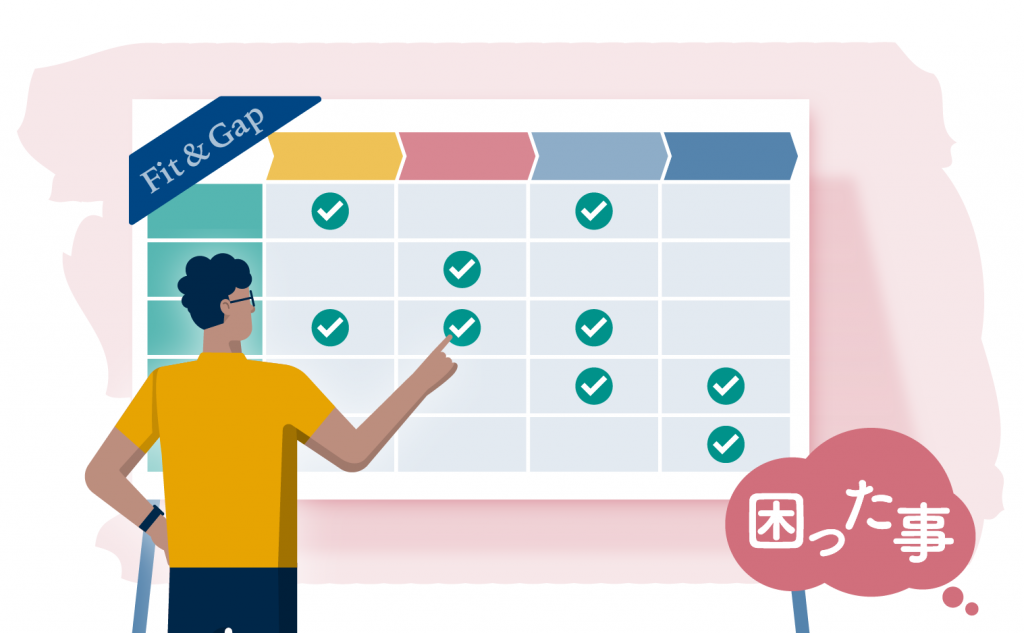
自分の課題がクリアできるか
何ができる・できない、というところから少し離れて、自分自身の課題がクリアできるかかどうか、という観点で考えるといいでしょう。
そのためには、まず計画要件を明確にすることです。そして、その要件に対して、Asprovaが対応できるかどうか検討します。
一般的には「Fit&Gap」表を作ることが多いようです。Fit&Gapとは、導入しようとするシステムと業務プロセスとのFit(適合)とGap(ズレ)を見いだし、分析することです。文章で表現しただけでは社内共通の理解が得られないので、具体的な検証が重要です。そのためにはプロトタイプ(試行)をやってみて計画要件を確認することが、一番の王道でしょう。
Asprovaでは、計画要件を入力して動作を確認することができます。データ化できない要件は、スケジューラでは扱えません。初めは簡単なデータで、最小限できることを確認するといいと思います。「大は小を兼ねる」と称して一番難しいことから着手するケースもあるのですが、そうするとなかなか前に進みません。簡単なことから進めるやり方を推奨します。
「できる・できない」を判断するとき、プロトタイプによる確認が大事なのは、個々の要件では「できた」ことが、組み合わせによってできなくなることもあるからです。たとえば、納期厳守の要件と作業負荷を守る要件は、資源の混み具合やシフト時間の関係で、できたりできなかったりします。逆に単独機能ではできなかった要件が、機能を組み合わせたり、式を用いることで実現することができることもあります。
1人で悩まずに相談を
プロトタイプで必要最低限なことができると確認したら、それ以降は一人で考えたり悩んだりしないことです。展示会やセミナーで、当社エンジニア、販売パートナーとお話しすると、一気に解消するかもしれません。オンサイト、オンラインと、いろいろな方法で話を聴けるようになりました。有効活用してもらえればと思います。
Asprovaを活用するには、課題をはっきりさせ、プロトタイプの実施を通じて段階的に進め、コミュニケーションを大切にすることで、スムーズに導入が進んでいくでしょう。
関連するナレッジセンター 困った事35 09 何ができて、何ができないのかわかりにくかった
(了)
コラム編集部
最新記事 by コラム編集部 (全て見る)
- 困ったこと35~作業指示と無関係に作業する人がいて困った - 2025年4月23日
- 困ったこと35~一生懸命やっているのに、理解してもらえなかった - 2025年4月23日
- 困ったこと35~「何でもできる」と思い込んでいる人に困った - 2025年4月23日

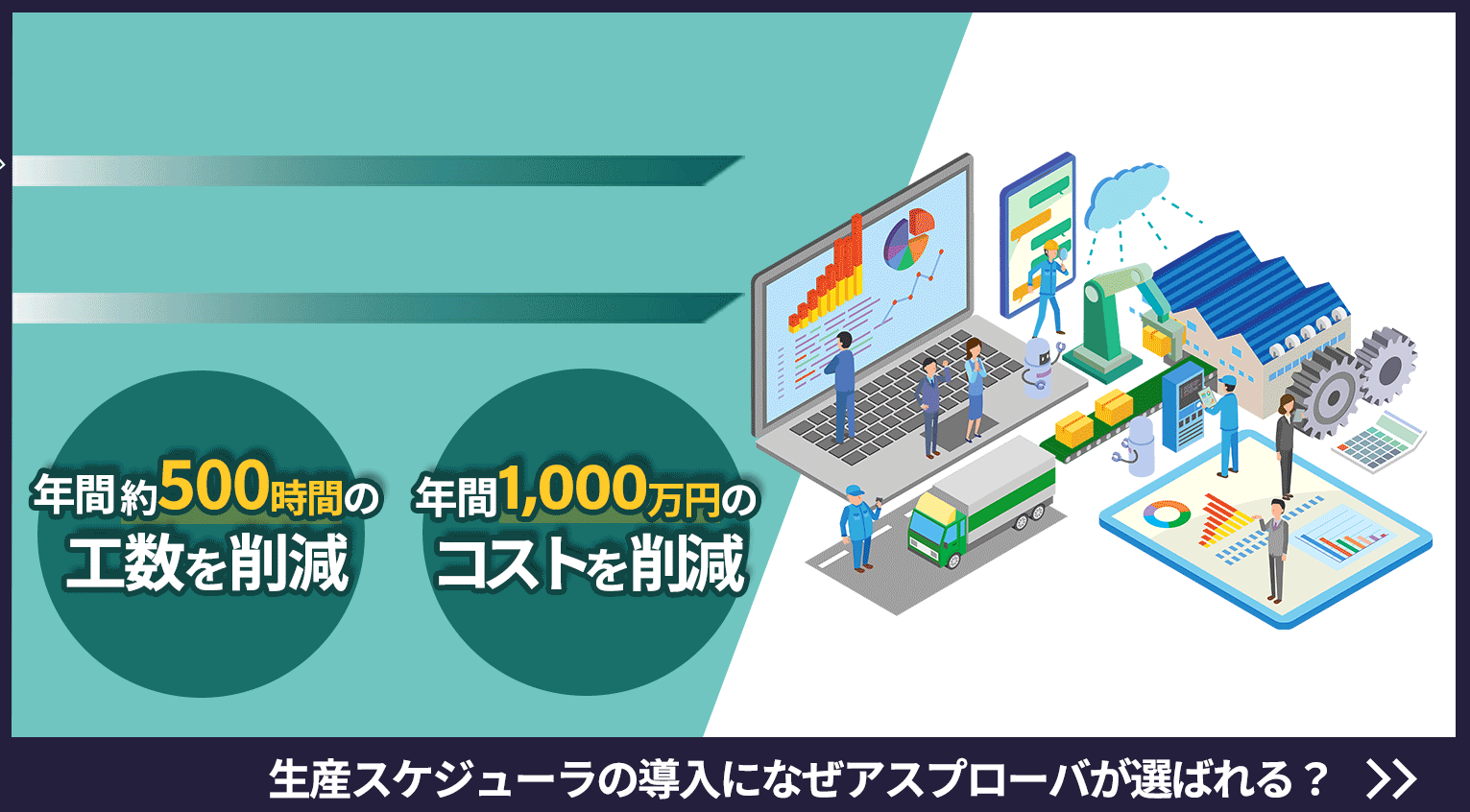
 困ったこと35~ 不良品、故障、オーダ急変…イレギュラーケースへの対応は
困ったこと35~ 不良品、故障、オーダ急変…イレギュラーケースへの対応は 複数工場・工程に生産スケジューラを導入するときのポイントとは?
複数工場・工程に生産スケジューラを導入するときのポイントとは? 困ったこと35~大日程計画・中日程計画・小日程計画…どこから始めたらいいのか迷った
困ったこと35~大日程計画・中日程計画・小日程計画…どこから始めたらいいのか迷った アスプローバのセミナーで学ぶ:外段取りを考慮した最適な生産スケジューリング
アスプローバのセミナーで学ぶ:外段取りを考慮した最適な生産スケジューリング 困ったこと35~費用対効果をどう示すか、後編
困ったこと35~費用対効果をどう示すか、後編 困ったこと35~スケジューラと稟議書~どうすれば通るか
困ったこと35~スケジューラと稟議書~どうすれば通るか