困ったこと35~作業指示と無関係に作業する人がいて困った
2025.04.23A3:生産スケジューリングの悩み相談せっかくいい計画がAsprovaによってできたのに、その通りに現場が動いてくれない。こんなケースもあります。それは人の問題、たとえば個人のキャラクターや職場の人間関係が原因なのかもしれません。でもそうではなくて、Asprova導入のやり方に問題があった可能性もあります。作業者を呼んで事情を聴く前に、今一度、状況をよく観察してみましょう。

目的と効果をみんなが知る
現場に指示を聞いてもらえない場合、計画側に起因する2つの理由が考えられます。
- Asprova導入の目的や効果が、製造現場に十分伝わっていない。
- 立てられた計画に、作業効率や作業のしやすさが考慮されていない。
1の対策は、いたってシンプルです。Asprova導入の目的や効果を、関係者みんなに周知徹底することです。生産計画表を作る人、計画表をもとに管理する人(資材、製造、品質管理など)、計画表をもとに作業する人と、さまざまな立場の人がかかわっています。具体的には次のようなことが挙げられます。
- 作業指示の明確化: 作業指示の中に、必要な情報がすべて含まれているかを確認し、作業者が理解しやすい形で伝えます。
- 進捗管理の強化: 作業の進捗状況を定期的に確認し、予定通りに作業が進んでいるかをチェックします。これで問題を早く発見できます。
- 教育・トレーニング: 作業者に対して、生産スケジューリングの重要性や作業指示の意義を教えます。理解が協力につながります。
- フィードバックの収集: 作業者からのフィードバックを受け入れ、指示内容やプロセスの改善点を検討します。今後の指示がより的確になるでしょう。
当然のことながら、生産に携わる人たちみんなの相互理解と協力が、とても大事です。
無理がないか再確認する
2に対する方策としては、生産計画に無理や過剰なところがないか、再確認をします。
Asprovaを導入する時は、理想的な計画にしようとして、全工程で最小のリードタイムや段取りを目指すことが多くなりがちです。そのため、製造現場の管理レベルや作業のしやすさまで考えが回らないことになってしまうことがあります。
初めからあまり欲張らない方が、うまくいくことが多いようです。導入の目的や効果を達成できる必要最低限の計画にして、製造現場に裁量を与えるのも効果的です。導入した企業の事例では、40もある全工程すべての計画立案を考えていたけれども、実際に5工程ほどのシンプルな計画を立てる方向に変更したケースがあります。また、日々の詳細な計画で指示を出すのではなく、1週間くらいの大まかな計画を立て、後は現場で調整するとしたケースもあります。
自社の生産管理レベルに合わせて、最低限の範囲から初め、必要により計画内容を進化させることが、成功に導くコツだと考えられます。
関連するナレッジセンター 困った事35 作業指示と無関係に作業する人がいて困った
コラム編集部
最新記事 by コラム編集部 (全て見る)
- 困ったこと35~作業指示と無関係に作業する人がいて困った - 2025年4月23日
- 困ったこと35~一生懸命やっているのに、理解してもらえなかった - 2025年4月23日
- 困ったこと35~「何でもできる」と思い込んでいる人に困った - 2025年4月23日

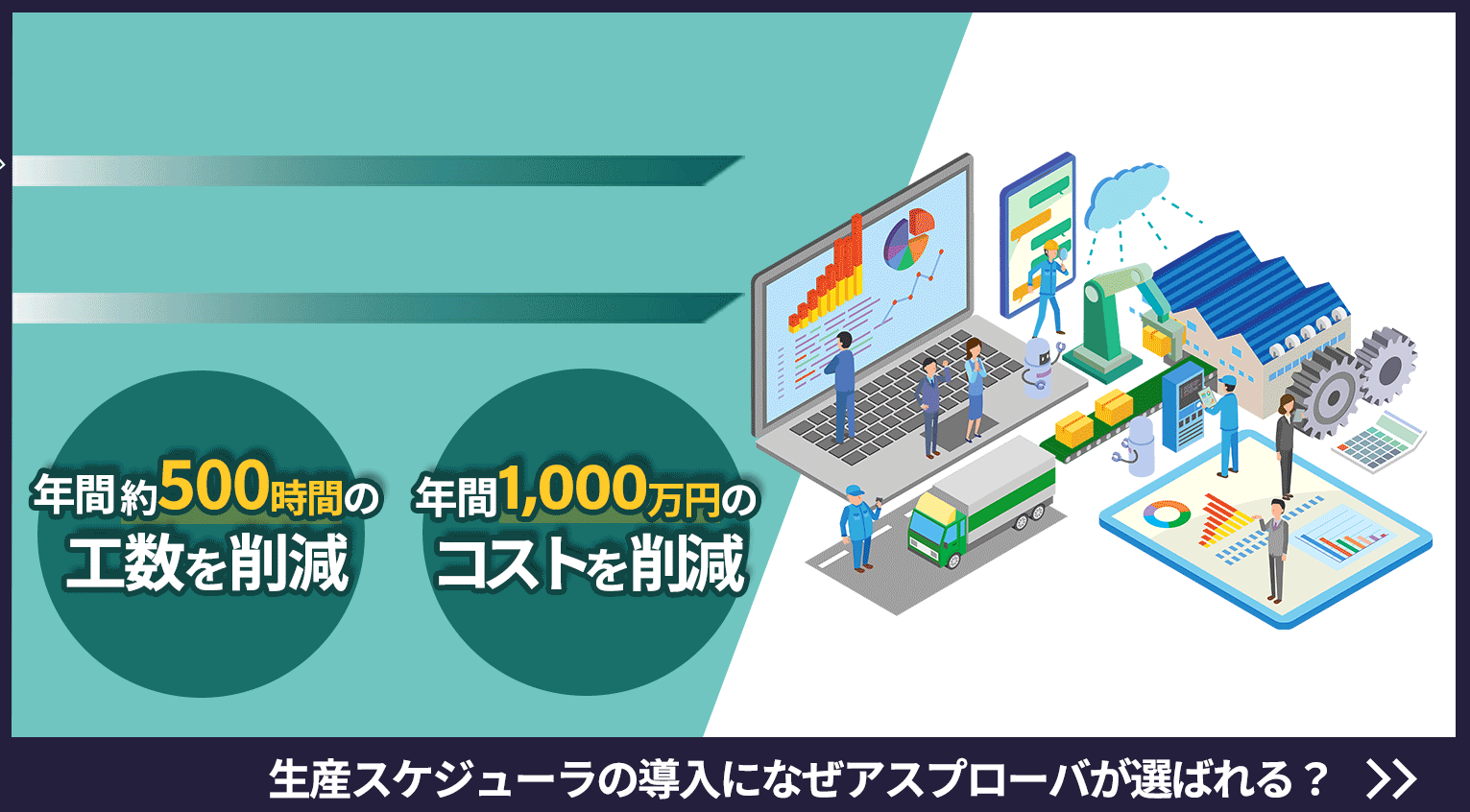
 困ったこと35~ 不良品、故障、オーダ急変…イレギュラーケースへの対応は
困ったこと35~ 不良品、故障、オーダ急変…イレギュラーケースへの対応は 困ったこと35~ 困っているときにサポートしてくれる人がいなかった
困ったこと35~ 困っているときにサポートしてくれる人がいなかった 困ったこと35~計画立案の役割や組織の見直しが必要になった
困ったこと35~計画立案の役割や組織の見直しが必要になった 困ったこと35~現状業務をどこまで変えたらよいかで迷った
困ったこと35~現状業務をどこまで変えたらよいかで迷った 困ったこと35~導入後の姿が想像しにくかった
困ったこと35~導入後の姿が想像しにくかった 生産スケジューラを導入すると、どんな効果が期待できますか?
生産スケジューラを導入すると、どんな効果が期待できますか?