困ったこと35~一生懸命やっているのに、理解してもらえなかった
2025.04.23A3:生産スケジューリングの悩み相談生産スケジューラの導入プロジェクトで「一生懸命やっているのに、理解してもらえない」という声を耳にします。生産現場と経営者の板ばさみになったり、現場に受け入れられなかったり、生産計画の担当者の苦労は尽きません。どうすればこうした悩みが解決するのか、考えてみましょう。

現場をなだめると経営側から不満が
初めに、ある文具メーカーの例を挙げます。生産計画を担当するIさんは、「10年間も理解してもらえなかった」といいます。納期優先、顧客ニーズ優先に向かって一生懸命やればやるほど、段取り回数が増加し現場作業の負荷増大を招き、作業者から理解してもらえなくなりました。心の離れてしまった現場作業者をプロジェクトに引き戻そうと、出来るだけ段取り回数が少なくなるようにすると、今度は納期遅延、リードタイム増長、在庫増大を招き、会社経営者側から不満が出る、というわけです。
どちらを一生懸命やっても理解は得られないという気の毒な事例です。その理由は、プロジェクト関係者の目指す方向が一致していないからだと考えられます。作業者は、自分がかかわる工程の稼働率向上と、作業負荷の軽減、そして自分が楽になることがプロジェクトのゴールと考え、本来の納期優先、顧客ニーズ優先には関心がないようです。プロジェクトに関係する全員がプロジェクトのゴールに向いていないと、このように困ったことが起きます。
この会社の場合は、その後、業務改革、ERP導入という全社プロジェクトが立ち上がり、否応なしに現場作業者も同じ方向を向かざるを得ない状況となりました。その流れでAsprovaもうまく立ち上がりました。
別の会社でも「当初まったく受け入れてもらえなかった。全社リードタイム短縮活動を契機に現場浸透を図った」「全社推進プロジェクトを立ち上げて、ベクトルを同じくする活動を実施した」といった事例があります。
トップダウンで導入し、全社の理解を図る
これらの事例から、まず、生産スケジューラの導入が会社全体に認知されていることが重要であることがわかります。いくら一生懸命やっても、経営者や管理者がその価値を理解していない限り、製造現場や関連部門で評価されません。プロジェクトチームを結成して、経営者や管理者および関連部門を巻き込むことです。プロジェクト体制、スケジュールを明確にして、導入の各段階で、経営者を含めたレビューポイントを設定し、プロジェクトの課題(費用、要員、業務改善など)を経営的な視点で明確にして、トップダウンで導入を進めることが必要です。
また、生産スケジューラの導入はサプライチェーンの全体最適と部分最適の葛藤になります。言い換えると総論賛成、各論反対になってしまうということです。
総論とは、顧客満足度の向上のために納期回答迅速化、納期遵守率向上や納入リードタイムを短縮するといったことです。また在庫削減のために生産リードタイムを短縮し、安全在庫基準を見直す、といったことも総論でしょう。
各論に該当するのは、設備、治工具、スキル、製品、仕様などです。たとえば、週次計画から日次計画や随時購買への変更は、業務工数が増加します。製造ロットサイズを最小化すると、段取り回数が増え、品質が不安定になるかもしれません。またリアルタイム工程進捗管理を導入すると、作業実績入力が煩雑になりそうです。
全体の意義や方向性には同意しても、その実施方法や詳細な計画には異論が出ることがあります。人々が納得するためには、全体像だけでなく具体的な実行計画や現実的な問題にも十分な説明と配慮が必要です。理解促進のための教育・トレーニングを実施することがおすすめです。また業務量の増加防止や各種のサポート機能を盛り込むことも、システムが歓迎され定着するために役立つでしょう。
コラム編集部
最新記事 by コラム編集部 (全て見る)
- 困ったこと35~作業指示と無関係に作業する人がいて困った - 2025年4月23日
- 困ったこと35~一生懸命やっているのに、理解してもらえなかった - 2025年4月23日
- 困ったこと35~「何でもできる」と思い込んでいる人に困った - 2025年4月23日

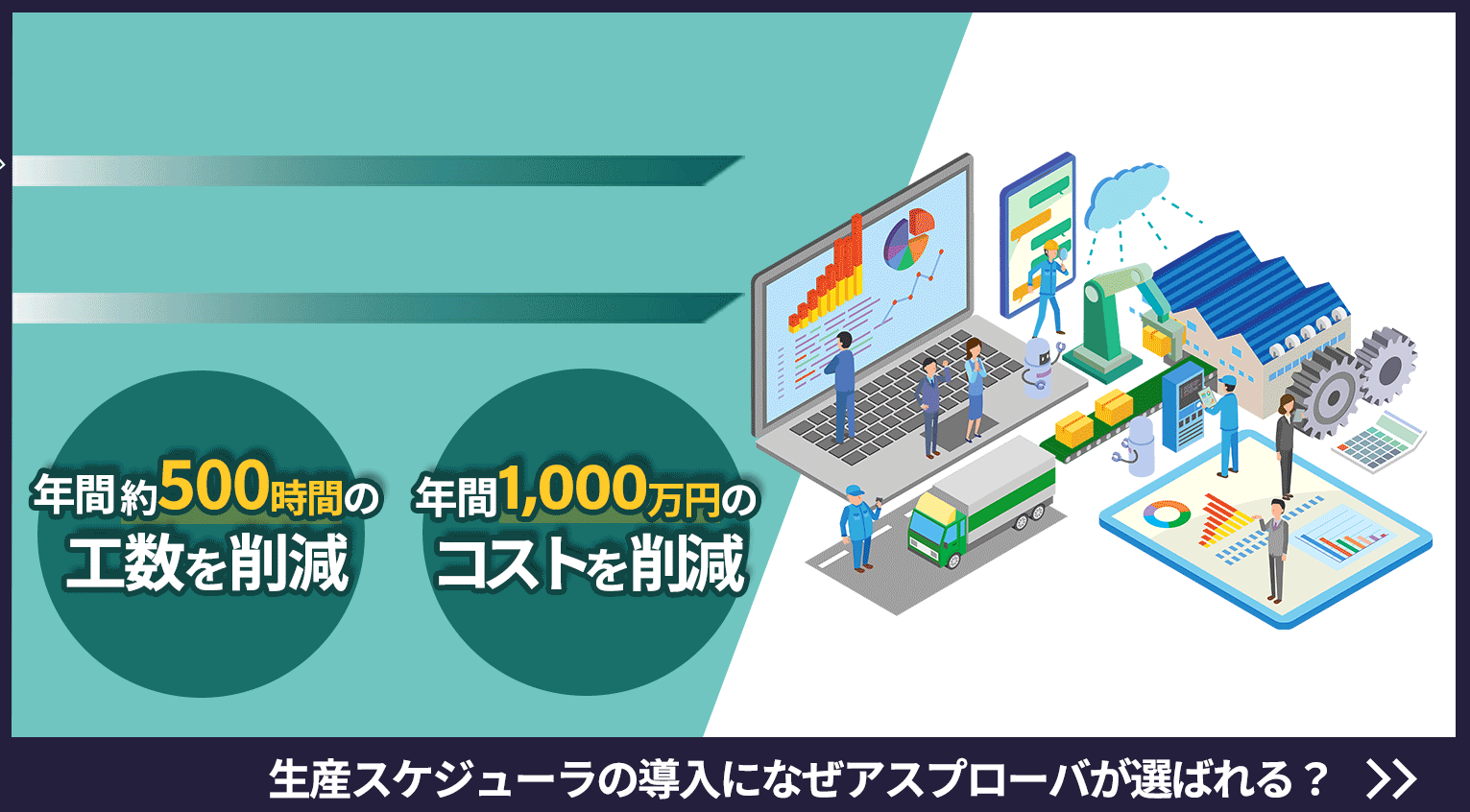
 困ったこと35~ 必須で難しい要件を後回し、最後に困った事態に
困ったこと35~ 必須で難しい要件を後回し、最後に困った事態に 困ったこと35~ システムテストは、どこでテストの完了かわからなかった
困ったこと35~ システムテストは、どこでテストの完了かわからなかった 困ったこと35~ Asprovaが属人化してしまった
困ったこと35~ Asprovaが属人化してしまった 困ったこと35~計画作成方法(コマンド、計画パラメタ)がわからなかった
困ったこと35~計画作成方法(コマンド、計画パラメタ)がわからなかった 生産スケジューラの導入を検討するには?
生産スケジューラの導入を検討するには? システム連携でお困りの方に、基幹業務システムとAsprovaの連携パターンを紹介
システム連携でお困りの方に、基幹業務システムとAsprovaの連携パターンを紹介